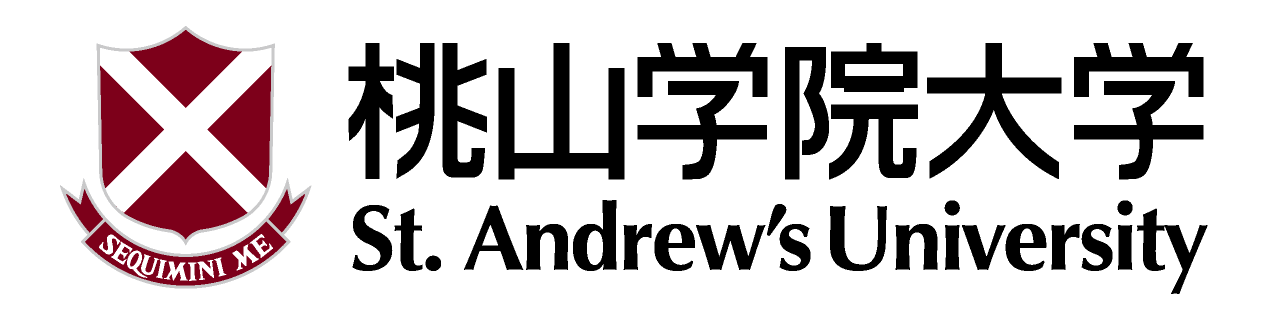報道関係者への夢と平和への想いから参加したルワンダ・フィールドスタディ
小さい頃から報道関係の仕事に憧れがあり、大学入学時は多角的な視野を身につけるため英語留学を考えていたのですが、国際センターでルワンダ・フィールドスタディが実施されていることを知りました。
私は沖縄県出身で、地元では幼い頃から慰霊祭や平和学習などがあり、「平和とは何か」ということについて学んできました。
今回参加したルワンダ・フィールドスタディのテーマが「平和構築」ということもあり、入学当初からの私の目的と、幼い頃からの「平和」に対する想いが重なり、英語留学ではなく、このプログラムに参加しました。

報道関係者を目指す渡具知さん
民族対立から起こったジェノサイド(大量虐殺)の歴史
ルワンダ・フィールドスタディに参加するまでは、ルワンダのことについて殆ど知りませんでした。事前学習の中で学んだのは、ルワンダで起こったジェノサイドの歴史です。
ルワンダにはもともと2つの民族が暮らしていたのですが、植民地支配をしていたベルギーが社会的階層の違いを利用し人為的に民族対立感情を煽った結果、ジェノサイド(大量虐殺)が起こりました。
武力や暴力の犠牲となった歴史を持つという点において、ルワンダは沖縄と似ているなと思いました。だからこそ、ルワンダの話を聞いたときは人ごとに思えませんでした。

ジェノサイドの銃痕が残るCamp Kigali博物館の建物にて

NTARAMA ジェノサイド記念館にて
ルワンダのプログラム
首都キガリを拠点にジェノサイドに関わるさまざまな博物館を訪れ、その歴史を学ぶプログラムです。
また農村地域を訪れ、現地団体が手掛けるマイクロセービング(小口貯金)を活用した農村開発プロジェクトの見学や現地の大学を訪問し現地学生との交流、サファリパークに行ってアフリカの大自然の中にいる野生動物の見学なども行いました。

首都キガリの街の様子

農村地域の様子

アフリカの大自然の中にいた野生動物
農村地域での開発プロジェクト
ルワンダの農村地域では、現地団体ARTCF(ルワンダキリスト教女性労働者協会)が実施する農村開発プロジェクトを見学しました。
このプロジェクトは、マイクロセービングと呼ばれる小口貯金の仕組みを導入し、30人ほどの住民がグループをつくり少額の現金を共同で積み立てています。
組合員は、この積立金を活用し融資を受け、小規模ビジネスの立ち上げや子どもの学費などに充てています。積み立て金から融資を受けた人は、利息をつけてグループに返済します。
住民の方々と交流する中で、人々がお互いに助け合いながら生活している様子を伺い、少し羨ましく思いました。
日本でも昔は住民同士が支え合って生活し、困ったときは協力し合う文化がありましたが、最近ではお互いに干渉しない傾向が強くなっているように思います。
この村に住む住民の方々の生き生きとした顔を見て、本当に豊かな社会とは人と人とのつながりや支え合い中に生まれるものだと感じさせられました。

農村開発プロジェクトについて説明する住民の方々

農村開発プロジェクトの組合員の方々とプログラム参加者たち
母国の平和のために本気で学ぶ学生との交流の中で
現地の大学にも訪問しました。その大学ではルワンダ人学生だけでなく、戦争や紛争が続く周辺諸国(スーダンやコンゴなど)からの学生たちも学びに来ていて、彼らの学びに対する意識の高さに、同じ大学生として驚かされました。
現地学生との交流の中で「平和運動とヘイト」というテーマで意見交換会を実施しました。私は平和活動の紹介を担当し、幼い頃から行っていた沖縄での米軍基地建設反対運動のことを紹介しました。
その際、現地の学生に「今日の日本の現状、特に沖縄の米軍基地の状況についてどう思いますか」という質問をしたのですが、彼らから「今の日本の防衛体制はアメリカに依存しすぎている。
米軍基地問題も第二次世界大戦の敗戦から学び、その意味を理解していれば現在まで続くような問題にはならなかったのではないか」と指摘され、他国のことなのにここまで真剣に考え、議論できるのかと驚かされました。
同時に、それができるのは彼らが母国の平和を取り戻すために本気で学んでいる学生だからだと感じました。

平和のため真剣に考える現地学生との意見交換会

ルワンダやスーダン、コンゴなどの学生たちとプログラム参加者
ジェノサイド被害者からの“Peace of mind”という言葉
プログラム参加前に本や映像、先生からの説明を通して知識を得ていたつもりでしたが、実際に虐殺の現場を訪れたときは、言葉では表せない事実の重みを感じ「30年前にこんなに恐ろしいことが実際にあったんだ」と実感しました。
現場を案内してくれていた女性ガイドさんがいたのですが、彼女もジェノサイド被害の当事者で、命からがら虐殺から逃れられたそうです。私は勇気を出して彼女に「怒りや憎しみは残っていないのですか」という質問をしました。
すると彼女は「確かに怒りをすべて消し去ることは難しいことかもしれません。でも、“Peace of mind”平和を願う心が大事なんだよ」と答えてくれました。
私はジェノサイドの加害者と被疑者が共に暮していくことは、過去の恨みや憎しみと共に生きるような複雑なことなのかなと思っていたました。でもガイドさんのその言葉は過去に囚われることなく、純粋に平和を願う想いが込められていて、私の想像していた答えとは全く違うものでした。
私にとってこの女性の言葉は「人の声を聞く」ということの大切さを再認識させてくれる貴重な体験となりました。

ジェノサイドの現場を案内する女性ガイドさん

“Peace of mind”を教えてくれたガイドさん
自分の「夢」が「覚悟」に変わった瞬間
報道関係者を目指す私にとって、ルワンダでの体験すべてが貴重な学びでした。
実は、このプログラムに参加する前は「私は本当に報道関係の仕事に就きたいのだろうか」という迷いがありました。
でもルワンダに行ったことで、現地に行かないと知ることができなかったこと、分からなかったことが沢山あるということに気づかされました。
また「現場に赴いて見聞きしたことを自分の言葉で発信する」ことの大切さを改めて感じましたし、自分の目で見るからこそ伝えられることがあると思いました。
ルワンダでの体験があったからこそ、「報道に携わる人間になりたい」という夢が、「報道に携わる人間になる」という覚悟に変わりました。

農村地域の子どもと

訪れた現地の小学校で関係者から話を聞く学生たち
隣の人の笑顔を守れる報道関係者に
4回生となり、就職活動を経て地元沖縄の報道関連企業に内定をいただきました。来春から念願だった報道の現場で働くことになりますが、私の目標は「隣の人の笑顔を守ることができる報道関係者になる」ことです。これは、ルワンダでの経験がきっかけで生まれた想いです。
プログラムに参加し、日常の中に隠れている小さな声や、ふとした瞬間にこぼれる人々の感情を見落とさないようにしたいと強く想うようになりました。
これからは報道の仕事を通じて、人々が見過ごしがちな問題や大切な瞬間に気づき発信することで、他者とのつながりを築くきっかけを作っていきたいと思います。

国際教養学部 英語・国際文化学科 4年生 渡具知 和奏さん
《参考》
ルワンダ・フィールドスタディ
ジェノサイドの歴史についての資料館の記録や生存者の証言からの学習、農村部の所得向上と和解醸成のための協同組合活動の見学、観光振興の一環としてのサファリ見学、小学校の訪問、現地大学生との交流などを行います。
現場体験を通じて、レイシズムやヘイトクライムに象徴される、現代社会が抱える分断と暴力の問題について考察し、紛争後の平和構築の実践的な取り組みについて学ぶプログラムです。